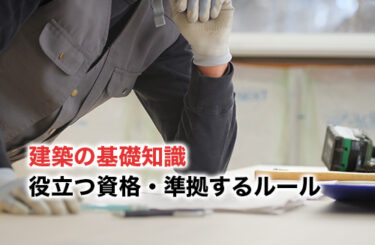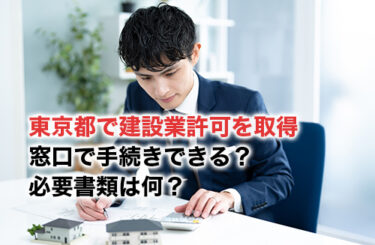日本を代表する巨大な「東京タワー」が、どのような課題を乗り越えて建設されたのかご存じでしょうか。また、現代では想像もつかない建築方法が採用されていた事実を知らない人も多いはずです。
この記事では、東京タワー建設の魅力を歴史をひも解きながらわかりやすくまとめました。
東京スカイツリーに並ぶ巨大建設物の魅力を知る参考にしてください。
東京タワーとは?

東京タワーは、日本を代表する巨大建設物のひとつであり、東京都港区の芝公園にそびえたつ赤い見た目が特徴的な建設物です。
とくに有名なのがタワーの高さであり、地上253mの自律鉄塔、80mアンテナ支持塔からなる合計333mで構成されています。巨大な鉄塔の建物構造にはすべて鉄骨が利用され、その重さがなんと3,680tもあり、小さな車(およそ1t)3,680台とほぼ同じ重さに比例するのが特徴です。
東京タワーと世界のタワーの違い
超大型な建設物である東京タワーですが、世界にはほかにも数多くの巨大タワーが設置されています。参考として、以下に有名な巨大タワーの高さをランキング形式で整理しました。
| ランキング | タワー名称 | 国 | 高さ |
| 第1位 | 東京スカイツリー | 日本 | 634m |
| 第2位 | 広州塔 | 中国 | 600m |
| 第3位 | CNタワー | カナダ | 553m |
| 第4位 | オスタンキノ・タワー | ロシア | 537m |
| 第5位 | 東方明珠電視塔 | 中国 | 468m |
実は、東京タワーは世界で24番目に高い建設物です。
以前までは東京タワーが日本で一番高い建設物でしたが、東京スカイツリーが建設されたことにより2番目に高い建設物へとランキングが下がってしまいました。
東京タワーの構造
東京タワーは、主部材を三角形に組み合わせて建設する「トラス構造」が採用されています。
また東京タワーのトラス構造は、部材同士を完全に固定しておらず「あそび」を設けた状態で建設されているのが特徴です。
部材同士に余裕を持たせることによって、地震の振動を受け流せるため、最上部まで揺れを届けない安全な構造として知られています。
また東京タワーに利用されたトラス構造は、のちに東京スカイツリーでも活用されているのが特徴です。技術の発展、そして安全性の向上により、東京タワーよりも300m近い高さまでトラス構造を建設できるようになりました。
建設・建築関連の知識に興味をお持ちなら、以下の記事をチェックしてみてください。
設計に関わる仕事内容や利用ツールについて解説しています。
東京タワー建設の目的

東京タワーは観光や高さ比べのために建設されたものだと思われがちですが、実はテレビやラジオの総合電波塔という目的で建設されています。
日本では東京タワーができる前まで、地方独自の電波塔によりテレビやラジオが放送されていました。そういったなか、東京にある電波塔は関東一円に電波を届けることができず、一部の地域でしかテレビやラジオを聞けなかったのです。
そして全国的なテレビ放送をスタートする流れを契機として始まったのが、遠くまで電波を届けられる巨大タワーの建設です。タワーの高さが高いほど遠くまで電波を届けられることから、関東一円に電波を届ける高さを計算し、333mの東京タワーが建設されることとなりました。
東京タワー建設の歴史
東京タワーが建設されたのは、今から60年以上前の1957年(昭和32年)です。
日建設計の設計のもと、竹中工務店が施工を担当しました。
東京タワーが建設の理由は前述したとおり、テレビ塔の電波拡大ですが、それをどのエリアに設置すべきなのかが問題となりました。現在、東京都港区の芝公園に建設されている東京タワーですが、次のような場所も候補に挙がっていたそうです。
- 東京都の上野公園
- 千葉県の鹿野山
しかし、維持管理の面から遠く離れた場所に建設するのは好ましくないこと、そして山地部での施工の場合、鉄骨の運搬が大変になるといった理由から、テレビ局・ラジオ局から距離が近い港区の芝公園が選ばれています。
1958年12月23日の開業より観光地としても有名に
東京タワーは電波塔としての目的だけでなく、世界的にも巨大な建設物の特徴を活かして観光地しても企画されました。開業してすぐに年間来場者が500万人を記録し、その後、次のような施設もオープンし、東京観光の有名スポットとして知れわたりました。
- 特別展望台(トップデッキ)
- 蝋人形館(閉館)
- 水族館(閉館)
また東京タワーには複合商業施設「フットタウン」が建設され、展望のみならず買い物やエンタメを楽しめる場所として、日本中・世界中の観光客が集まる場所として不動の地位を築きました。
2008年に東京タワーが大規模リニューアル
東京タワーの人気を継続させる目的として、開業50周年を迎えた2008年にはタワー内施設の大規模リニューアル工事が進められました。
エレベーター移動中も楽しめるようにテーマ性をもたせたデザインへと一新したり、タワー構造の安全性を図るために、鋼板の補強工事や塔全体の塗り替え工事などが実施されています。
東京タワー建設の雑学

真っ赤な見た目をした日本のシンボルである東京タワーですが、建設に関して今では考えられない面白い話題が数多くあることをご存じでしょうか。参考として、人に話したくなる面白い話題を4つ紹介します。
東京タワーは命綱なしで建設された
東京タワーの建設に関わるとび職人たちは、安全帯(落下を防止するアイテム)を装着せずに、命綱なしで工事をしていたとご存じでしょうか。
東京タワーの建設では、最大333mの高さを工事しなければなりません。
しかし当時は工事中の安全に関する取り決めがないほか、命綱を付けると建設工事に大幅な遅れが発生するため、命綱を付けないまま工事を進めることとなりました。
また、強風が吹く高所作業が多い現場であるにも関わらず、墜落して亡くなった人はたったの1人だと言われています。現代では完全にNGですが、命綱がなかったことからたった15ヶ月でハイスピードな突貫工事を完了できたのかもしれません。
東京タワーの所有者は民間企業
東京タワーは日本を代表する建設物であることから、国が所有・管理しているものだと思われがちですが、実際には民間企業である「日本電波塔株式会社」が所有する建設物です。
また、東京タワーの筆頭株主は東映そしてマザー牧場となります。
民間企業によって維持管理が進められており、株主総会でも民間企業が意向を決めるため、国のかかわりがほとんどない電波塔なのです。
東京タワーは正式名称ではない
東京タワーはそのままの名前で親しまれている建設物ですが、実は「日本電波塔」が正式名称です。
東京タワーは建設物の相性であり、完成当初は日本電波塔という名前で広める予定でした。
しかし、観光向けの施設提供も兼ねていることから、開業年に東京のシンボルを意味する「東京タワー」という名前が採用され、現在では東京タワーという名前だけが広まっています。
東京タワーの色は赤ではなくオレンジ
東京タワーと言えば赤色の見た目が特徴的な建物ですが、実際には赤色ではなく「インターナショナルオレンジ」という色が採用されています。
これは航空法によって定められている色であり、近くで実物を見ると赤ではなくオレンジ色をしていることがわかります。また、タワーが赤く見えるのは、人間の目が赤色だとイメージしてタワーを見ていることや、太陽光の反射の影響を受けて赤みがかって見えると言われています。
東京タワー建設で抱えていた課題

東京タワー建設は15か月という短期間で完成した巨大タワーとして有名です。
しかしその裏では、設計や工事に関してさまざまな課題を抱えていました。
現在も鎮座している東京タワー建設の裏側を、詳しく解説します。
短すぎる納期
通常、東京タワーのような巨大建設物をつくるためには何年もの時間をかけながら安全に建設していくのが一般的です。しかし設けられていた工事期間はたったの15ヶ月であり、設計期間もたったの3ヶ月だったそうです。
東京タワーの設計を担当したのはベテラン建築家である「内藤多仲」氏であり、3ヶ月の間に合計1万枚もの設計図を書き上げたという逸話があります。
また現代では、CADやBIMといったソフトを使って設計するのが一般的です。
図面の種類や書き方について知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
手戻り不可能な状態で建設工事がスタート
ハイスピードで設計された東京タワーは、すぐに施工会社に渡され工事がスタートしました。
しかし、建設工事はひとつ間違えると取り返しがつかない事態に発展するのが常です。
対して、今回の建設工事では小さなミスもなく進み、完成後に実施された検査では、鉄骨同士の接合部のズレが15mmだけズレている程度に収まりました。急ぎつつも正確な作業を進められた当時の技術は現在も引き継がれ、スカイツリーに応用されています。
手計算による構造計算の実施
構造計算について、現在では専用のシステムを使って手軽に実施できるようになりましたが、当時はまだ手計算が主流でした。もちろん東京タワーも手計算ですべての構造計算が実施されており、最終的な計算チェックもすべて人間の力だけで遂行されています。
3ヶ月間しか与えられていなかった設計期間の影響もあり、昼夜を問わず設計することが続き、業務の終盤には三日三晩、事務所に缶詰となって従業員と協力し合いながら設計業務を遂行されたそうです。
また急いでいたのにもかかわらず、構造計算にミスはありませんでした。
東京タワーは現在でも大型地震や台風に負けることなく、安全な状態を維持し続けています。
さらに建設・建築のことを知りたい、BIM・CIMといったソフトに興味があるという方は、BIM/CIM研究所のまでお問い合わせください。ソフト提案やセミナー紹介などをサポートいたします。
東京タワー建設についてまとめ
華やかな見た目をした東京タワー建設の裏では、設計者・施工者による熱いドラマが繰り広げられていました。
今回紹介した東京タワー建設の情報はすべて実際に起きた歴史です。
現在との建設の考えと違う点が多いことはもちろん、建設の話題になる面白い豆知識が多い建設物ですので、この機会に東京タワーの魅力を再認識していただけると幸いです。